【経営者向け】新卒採用ターゲット設定の方法|理想の学生を確実に集める3ステップ
新卒採用でターゲット設定はなぜ必要なのか
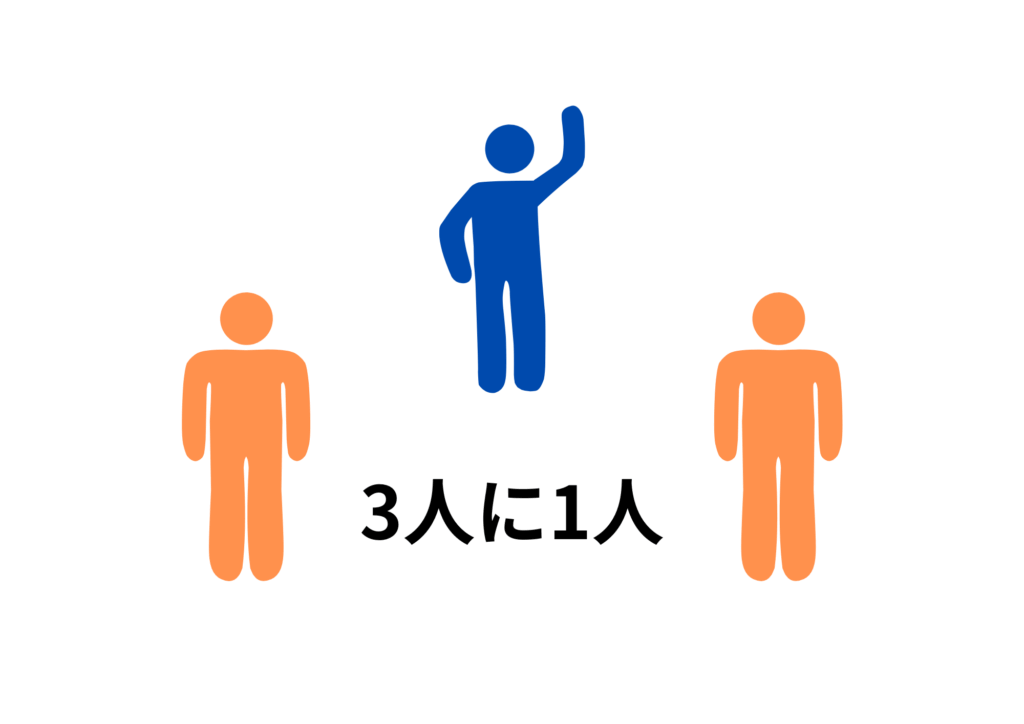
当社では、新卒採用は企業にとって「未来への投資」であり、単なる人員補充ではないと考えています。なぜなら、採用する人材の方向性次第で、将来の組織の成長や企業文化までもが大きく左右されるからです。だからこそ、どんな人材を採用したいのか――つまり採用ターゲットを明確にすることが欠かせません。しかし現実には、このターゲット設定が曖昧なまま採用活動を進めてしまう企業も少なくなく、その結果、ミスマッチによる早期離職や成果につながらない人材の採用といった課題に直面しています。
実際に、令和5年厚生労働省の調査によると、大卒就職者の3年以内離職率は31.5%に達しています。これは「3人に1人が3年以内に辞めている」ことを意味しており、日本の新卒採用市場が抱える大きな課題の一つです。新卒社員が3年以内に離職した場合の企業損失額は約300万~500万円にも及びます。
離職率の高さの背景には、「採用時に描いた人物像」と「入社後に求められる人物像」の間に大きなギャップがあることが挙げられます。つまり、採用ターゲットを明確にしないまま採用を行うと、学生側も「思っていた仕事と違う」と感じ、企業側も「期待していた活躍が見込めない」となるのです。
「採用は毎年同じように行いがちですが、会社も市場も変化しています。だからこそ“今の自社にとって合う人材は誰か”を毎年見直すことが欠かせないのです。」
この言葉の通り、ターゲットを明確にすることは、採用活動を単なる「数合わせ」から「戦略」へと昇華させます。例えば某IT企業では、以前は「優秀そうに見える女子学生」を多く採用していました。しかし、彼女たちは仕事内容ではなくオフィス環境や立地条件に魅力を感じて入社していたため、数年以内に離職してしまうケースが相次ぎました。分析の結果「男子学生のほうが仕事内容に魅力を感じ、腰を据えて働く傾向がある」と分かり、ターゲットを変更したところ定着率が改善したのです。
このような例は珍しくありません。重要なのは「理想の学生像」を思い込みで決めるのではなく、データ・現場の声・経営の視点を組み合わせて明確に定義することです。 では具体的に、どのようにして採用ターゲットを明確化していけばよいのでしょうか。ここからは、その手順を3つのステップに分けて解説していきます。
【Step1】過去の採用分析と振り返り

採用ターゲットを設定する最初のステップは、「過去の採用データを徹底的に振り返ること」です。
ある企業では、過去の応募データを分析した結果、エントリー数が増えても、実際に定着した人材は限られていることが分かりました。特に、ある大学の男子学生の採用率が高く、しかも長期的に成果を出している傾向が見られたのです。逆に、特定の属性の学生は採用こそされるものの、1〜2年で離職してしまうケースが多発していました。このデータをもとに採用ターゲットを修正した結果、面接通過率や定着率が大幅に改善しました。
厚生労働省が公表している「雇用動向調査」でも、業界別・性別・年齢層別に入職率・離職率がまとめられており、自社のデータと照らし合わせることで、自社が相場と比べて離職しやすいのか把握できるものになっています。
さらに、振り返りには「活躍している社員の共通点」を探すことも重要です。例えば営業職で成果を出している人の特徴を洗い出すと、「リーダーシップ経験がある」「部活動で主将を務めた」「アルバイトで長期間働いた」などの具体的な要素が浮かび上がります。こうした要素は、単なる学歴や学部以上に「定着」と「活躍」に直結するのです。 ここで経営者に問いかけたいのは、「自社の過去5年の採用で、どんな学生が定着し、どんな学生が辞めていったかを言語化できていますか?」という点です。もし即答できないのであれば、まずはデータの可視化から始めるべきでしょう。
【Step2】ターゲットへ率直な想いを伝える
ターゲットが定まったら、その学生層に向けて「なぜあなたに来てほしいのか」を明確に伝えることが必要です。
採用現場でよくある失敗は、「素直で協調性のある人」など抽象的な言葉で学生に訴えかけることです。これは「恋愛で『優しい人が好き』と言っているのと同じで、誰にでも当てはまってしまう」ものです。
実際に効果があった例として、明確なモデル社員を決める取り組みがあります。例えば、某IT企業では「男子学生」をターゲットに定めた後、会社説明会に最も学生と年齢の近い若手社員を登壇させました。これにより、学生は自分の将来像を具体的にイメージでき、その後の面接希望者が増えました。。
さらに効果的なのは「エピソードで語ること」です。例えば、「この会社では失敗してもすぐにリカバリーできる力が求められる。実際に◯◯さんは入社1年目で大きな失敗をしたが、仲間と協力して2週間で立て直した」という具体例を伝えることで、学生は「自分も挑戦してみたい」と感じます。
リクルートワークス研究所の調査(2024)によると、学生が企業を選ぶ際に重視するポイントは「成長できる環境」「社員の人柄」「仕事内容のやりがい」が上位に挙がっています。つまり、給与や福利厚生よりも「リアルな仕事体験」に近い情報が刺さるのです。 ターゲットへ想いを伝えることは、マーケティングで言う「お客様にとってのメリットを示すこと」ことに近い行為です。経営者自身が「なぜこの学生に来てほしいのか」を言語化し、発信することで、採用メッセージは格段に強くなります。
【Step3】常に社内で話し合う
ターゲット設定は一度決めて終わりではなく、継続的に見直す必要があります。市場や学生の価値観は毎年変わり、会社の事業フェーズも変化するからです。
例えば、ある企業では以前「高学歴学生」にこだわって採用を行っていました。しかし実際には学歴と成果が必ずしも比例せず、むしろ「チームで協働できる人材」の方が活躍していると分かりました。そこで「失敗経験のある学生」「部活動で主将を務めた学生」といった具体的な人物像にターゲットを変更した結果、離職率が下がり、定着率が改善しました。
また、厚労省の「若年者雇用対策」の調査でも、若手社員の早期離職理由のトップは「入社前に抱いていたイメージと実際の仕事のギャップ」です。このギャップを埋めるためには、社内でターゲットを共有し、経営・人事・現場が一体となって採用戦略を考えることが不可欠です。
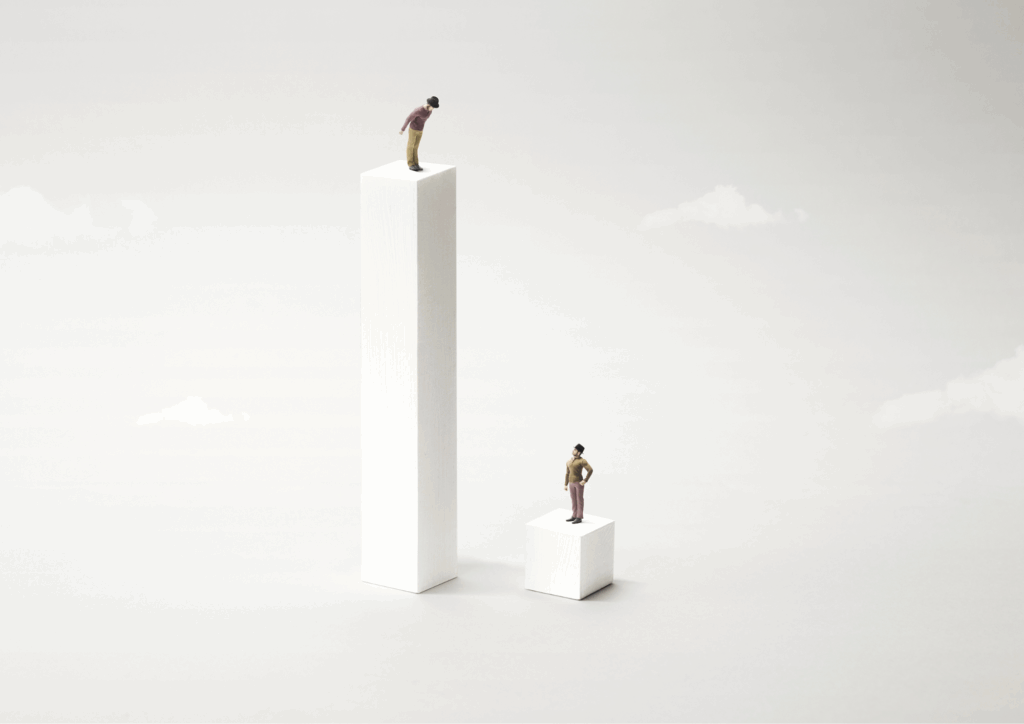
採用に成功している企業の多くは年に数回、採用チームと現場リーダーを交えた会議を開き、「今年のターゲットは本当にこれで良いのか」「去年採用した人は定着しているか」を議論しています。このような定期的な対話こそが、採用の成功率を高める鍵なのです。
まとめ:ターゲット設定が「応募数」と「定着率」を変える

新卒採用において、ターゲット設定は「採用の効率化」だけでなく、企業の未来そのものを左右する重要な戦略です。ここまで見てきたステップを総合すると、ターゲット設定が果たす役割は大きく3つに整理できます。
第一に、採用効率の向上です。
ターゲットを明確にすれば、不要な母集団形成にかける時間やコストを削減できます。例えば「理系出身で基礎研究より応用開発に関心がある学生」をターゲットとすれば、合同説明会で漠然とした訴求をするよりも、特定の学部やゼミに的を絞ったアプローチが可能になります。結果として、応募数は減っても「面接に進む学生の質」が向上し、採用活動全体の効率が上がるのです。
第二に、定着率の向上です。
初めに述べた通り、大卒新卒者の3年以内離職率は31.5%に上ります。この背景には「仕事の実態と入社前の期待とのギャップ」があります。ターゲットを明確にした企業は、学生に対して「どんな人材を求め、どんな環境を用意しているか」を率直に伝えるため、入社後のギャップが少なくなります。採用段階から相互理解が進むため、学生も企業も「ミスマッチのない選択」ができ、結果的に離職を防ぐことにつながります。
第三に、社内の一体感を生み出すことです。
ターゲット像を明確にし、それを経営・人事・現場が共有することで、採用から育成まで一貫性のある方針を持つことができます。採用担当者だけが「こういう人が欲しい」と考えていても、現場で必要とされる人物像とズレていれば意味がありません。定期的に社内で「今年のターゲット像は妥当か」を議論することで、社員全体に共通認識が生まれ、迎え入れた新入社員を組織全体で支える土台ができます。
これら3つの効果は相互に関連しています。効率的に採用した学生が定着し、さらに組織全体で支える体制があれば、企業は採用のサイクルに安定性を持つことができます。逆に、ターゲットが曖昧なまま採用を続ければ、毎年「人が辞めるから採る」という繰り返しに陥り、長期的な人材戦略を描けなくなります。
経営者にとって重要なのは、「採用ターゲット設定は人事部の仕事ではなく、経営そのものに直結するテーマである」と認識することです。どのような人材を採るかは、その企業が10年後にどのような組織になっているかを決定づける要素です。実際に、採用ターゲットを見直した企業の中には、数年後に事業拡大や新規プロジェクトの成功につながったケースも少なくありません。逆に、採用戦略を軽視して人員を「とりあえず補充」していた企業では、事業成長の機会を逃すこともあります。
最後に、これからターゲット設定を考える企業への提案として3つの問いを投げかけたいと思います。
- 自社の過去5年間の採用実績から「活躍している人材の特徴」を言語化できていますか?
- 学生に対して「なぜ自社に来てほしいのか」を、抽象的ではなく具体的なエピソードで伝えていますか?
- 採用ターゲット像を経営・人事・現場で共有し、毎年アップデートする仕組みを持っていますか?
これらの問いに答えを出していくことこそが、採用活動を「単なる人員確保」から「未来を創る投資」へと変えていきます。新卒採用は未来への入り口です。誰を迎え入れるかで、10年後の企業の姿は大きく変わるでしょう。だからこそ、今こそ「採用ターゲット設定」を経営戦略の核心に据えることが求められています。
新卒採用の成功は「誰を採るか」を明確にすることから始まります。ターゲットを定めることで、ミスマッチによる早期離職を防ぎ、採用活動の成果を最大化できます。
株式会社エンライブンでは、これまで関西エリアを中心に多くの企業様をご支援してきました。実際に、
- 過去の採用実績を振り返り、活躍している人材の特徴を整理すること
- 学生に「なぜ自社に来てほしいのか」を、具体的なエピソードで伝えられるようにすること
- 採用ターゲット像を社内で共有し、毎年見直せる仕組みをつくること
といった取り組みを、一緒に考えながら形にしています。
「ちょっと自社の採用ターゲットを見直したいな」「他社はどう工夫しているのか知りたい」――そんな段階でも大丈夫です。貴社に合った方法を一緒にお探しいたします。
こちらよりお気軽にご相談ください。
【参考リスト】
厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況」https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35683.html
厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況」https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35683.html
リクルートワークス研究所「就職白書」(2024)https://www.works-i.com/research/
厚生労働省「雇用動向調査」https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/11-23.html
経済産業省「雇用政策」https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/index.html